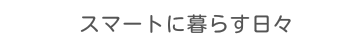お部屋をすっきりと整えたい。そう思って収納に取り組み始めても、「どこから手をつければいいか分からない」「片付けてもすぐに元に戻ってしまう」と悩むことはありませんか。
暮らしの中には、毎日使うお気に入りのものもあれば、あまり人目につけたくない日用品もあります。それらをすべて隠してしまうと使いにくく、すべて表に出しておくと雑然として見えてしまいがち。
大切なのは、「見せる収納」と「隠す収納」、それぞれの特徴を理解し、自身の暮らし方やお部屋の用途に合わせて、そのバランスを上手に取ることです。
この記事では、2つの収納方法の基本的な考え方から、リビングやキッチンなど、場所ごとの具体的な実践アイデアまで、暮らしが整うヒントを丁寧にご紹介します。
まずは小さなところから、ご自身に合った方法を見つけてみませんか。
見せる収納と隠す収納の特徴を理解する

お部屋を快適な空間にするためには、まず「見せる収納」と「隠す収納」の基本的な特徴を知り、それぞれの良さを活かすことが大切です。
「見せる収納」は、その名の通り、物が見える状態(オープンな状態)で収納する方法です。
例えば、壁に取り付けた棚やフック、中身が見えるガラス扉のキャビネットなどがこれにあたります。お気に入りの雑貨を飾るように楽しんだり、よく使うものをすぐに手に取れるように配置したりするのに適しています。
一方、「隠す収納」は、扉付きの棚や中身が見えないボックス、引き出しなどを使い、外から物が見えないようにしまう方法です。
生活感が出やすい日用品や、色・形が雑多な細々としたものをすっきりとまとめるのに役立ちます。視界に入る情報が減るため、お部屋全体を整然とした印象に見せることができます。
見せる収納が向いている実用品
見せる収納は、毎日よく使う実用品や、デザインそのものを楽しみたいものに向いています。
たとえば、キッチンで頻繁に使う調理器具(お玉、フライ返し、菜箸など)や、使い勝手の良い鍋、素敵な柄の食器などは、あえて見える場所に置くと、使いたいときにすぐに手に取れて便利です。
調理の効率も上がりますし、どこに何があるか一目で分かるため、「探す」という手間を減らすことにも繋がります。
また、リビングで読む機会の多い雑誌や、表紙がきれいな本、お気に入りの雑貨や観葉植物なども、飾りながら収納する「見せる収納」に適しているでしょう。
ただし、見せる収納は、ただ置けばよいというわけではありません。
置く物の色合いや素材感を揃えたり、置く量を厳選したり(例えば、棚のスペースに対してゆとりを持たせる)することが、雑然とした印象を与えないための大切なポイントです。
また、見える状態であるため、こまめにホコリを払うなど、清潔さを保つ意識も必要になります。
隠す収納で扱いやすくする方法
隠す収納は、お部屋をすっきりと整然と見せたいときに、とても有効な方法です。
視覚的なノイズ(ごちゃごちゃとした印象)を減らし、落ち着いた空間を作るのに役立ちます。また、日用品のストックや、たまにしか使わない季節のものなどを、日焼けやホコリから守るという側面もあります。
しかし、単にしまい込んで見えなくするだけでは、どこに何があるか分からなくなり、かえって使いにくくなってしまうこともあります。
隠す収納を上手に活用する最大のコツは、「見えない場所こそ丁寧に整える」こと。
具体的な手順としては、まず「分類」から始めます。引き出しやボックスに入れる前に、まずは「何が」「どれくらい」あるかを把握し、用途や使う頻度ごとに仲間分けをします。
次に、その分類に合わせて「仕切る」工夫をします。例えば、引き出しの中には小さな仕切りトレーを設けたり、大きな収納ボックスの中は、さらに小さなケースで仕切ったりするなどです。物が混ざり合うのを防ぎ、定位置が決まりやすくなります。
そして、中身が一覧できない収納用品には、外からでも中身が分かるように簡単な目印(ラベルなど)をつけることを検討します。こうすることで、家族の誰もが分かりやすく、出し入れがスムーズになります。
「隠す」ことと「使いやすく整える」ことをセットで考えると、きれいな状態を無理なく保ちやすくなります。
空間に合わせて収納方法を選ぶ流れ
お部屋全体の収納方法を選ぶときは、まずその空間で「どのように過ごしたいか」「何を一番大切にしたいか」を具体的に思い描いてみましょう。
例えば、リビングは家族みんなが集まり、ゆったりとくつろぐ場所にしたいとします。
その場合、リラックスを妨げるような細々とした日用品や書類などは、できるだけ「隠す収納」ですっきりとさせることが考えられます。そして、くつろぎの雰囲気を高めてくれるような、お気に入りの雑貨や植物、写真などだけを厳選して「見せる収納」にします。
キッチンであれば、「効率よくスムーズに料理をしたい」という目的かもしれません。
その場合は、使用頻度の高い調理器具や調味料は「見せる収納」で取り出しやすくし、使用頻度の低い調理器具や食器、食品のストックなどは「隠す収納」でまとめておく、というバランスが考えられます。
このように、まずはその場所の「目的」を明確にし、それに合わせて「見せるもの(見えても良いもの)」と「隠したいもの(隠した方が快適なもの)」を分けていきます。
その上で、「見せる」と「隠す」の割合(バランス)を決めていくと、ご自身やご家族にとって最適な収納スタイルが見つかりやすくなります。
リビングとキッチンで使える収納の工夫

毎日多くの時間を過ごすリビングやキッチンは、家族が集まり、たくさんの物が動く場所です。
ここでは、それぞれの場所で役立つ、具体的な収納の工夫を見ていきましょう。
実用品を取り出しやすく見せて置く方法
リビングでは、読みかけの雑誌や新聞、空調などの操作に使う機器(リモコン類)、ティッシュペーパーの箱など、すぐに使いたい実用品がいくつかあります。これらは、それぞれに専用の置き場所(定位置)を決めておくと便利です。
例えば、リモコン類はデザインの素敵なトレイやお気に入りの浅いかごの上にまとめて置くだけでも、定位置が決まり、すっきりと見えます。トレイごとなら、お掃除の際にまとめて動かせるという利点もあります。
キッチンでは、調理中に使う実用品の「見せる収納」が特に役立ちます。使用頻度の高い調理器具(お玉やヘラなど)は、コンロの近くの壁にフックなどで「吊るす収納」にすると、場所を取らず、使いたいときに素早く手に取れます。
塩や砂糖などのよく使う調味料は、見た目の揃った容器に移し替え、作業台のすぐ手に取れる場所に並べておくのも良いでしょう。
ただし、コンロの近くは油はねや熱の影響を受けやすいため、置く場所や素材には注意が必要です。
動線を妨げない隠す収納のまとめ方
動線(人が室内を移動する経路)を意識することは、快適な暮らしと収納を考える上でとても大切です。
特に、リビングやキッチンのような活動の中心となる場所では、動線を妨げない収納計画が求められます。
隠す収納の場合、扉や引き出しを開け閉めするためのスペース(動作スペース)が必要になります。
収納家具を置くことばかりに気を取られ、この動作スペースを忘れてしまうと、「引き出しが最後まで引き出せない」「扉を開けると通り道がふさがってしまう」といったことになりかねません。
リビングであれば、ソファからテレビへの動線、あるいは部屋の入り口からベランダへの動線など、主な通り道には物を置かないのが基本です。
キッチンでは、一般的に「冷蔵庫」「シンク」「コンロ」を結ぶ三角形の動線(ワークトライアングルと呼ばれます)が、作業効率の鍵とされます。この動線を遮るような場所に、大きな収納家具やゴミ箱などを置かないように注意しましょう。
棚やボックスを床に直接置くと、通り道の邪魔になったり、お掃除がしにくくなったりすることもあります。
壁面を上手に利用したり、キャスター付きの動かせる収納を選んだりするのも一つの方法です。
棚やボックスの配置を決める考え方
収納用品を配置するとき、また収納用品の中に物をしまうときは、「使う頻度」と「物の重さ」を基準に考えると、安全で使いやすい配置になります。
一般的に、人が立ったままで、腕を伸ばしたり屈んだりせずに楽に手が届く高さ、つまり「目線から腰の高さあたり」が、最も使いやすい範囲(ゴールデンゾーンとも呼ばれます)とされています。
この高さには、毎日使う食器や、リビングで頻繁に取り出す書類など、一番使用頻度の高いもの(一軍)を置くのが基本です。
逆に、使う頻度が低いものは、少し取り出しにくくても構いません。例えば、頭上などの上段には、軽くてたまにしか使わないもの(お客様用の食器、季節の飾り物、ティッシュなどの軽いストック)をしまいます。
膝下などの下段には、重いものを収納するのが原則です。飲料のストックや大きなお鍋、使用頻度の低い家電製品などは、下の方に収納すると、棚全体が安定し、出し入れの際の身体への負担も少なくなります。
この「使いやすい高さ=よく使うもの」「上段=軽いもの」「下段=重いもの」という考え方は、リビングの棚でも、キッチンの食器棚やパントリー(食品庫)でも共通して活用できます。
小さなスペースを活かす収納テクニック

お家の中には、リビングやキッチンのような広い空間だけでなく、玄関、洗面所、ワークスペースといった、機能が限定された小さなスペースもあります。
こうした限られた場所を上手に活かす収納テクニックをご紹介します。
玄関やワークスペースの省スペース整理
玄関は、家の「顔」とも言える場所ですが、スペースが限られている割に、靴、傘、鍵、掃除道具など、置きたいものが多い場所でもあります。
こうした場所では、床面積を使わずに収納力を上げる「壁面」を活用しましょう。
例えば、壁にフックを取り付けて、鍵や靴べら、折り畳み傘などを「吊るす収納」にすると、場所を取らず、外出時にさっと手に取れます。
靴箱の扉の裏側も、粘着式のフックやバーを取り付けることで、スリッパや小物類の収納スペースとして活用できる場合があります。
また、在宅でのお仕事などで使うワークスペース(作業空間)では、机の上が書類や文房具で散らかりがちです。作業スペースが狭いと、集中力にも影響が出ることがあります。
書類や本、ノートなどは、平らに積んで(平置きする)とかさばるため、「立てる収納」を意識すると良いでしょう。ファイルボックスやブックスタンドを活用して縦に並べることで、少ないスペースでも整理しやすくなり、必要なものをすぐに見つけ出せます。
すき間を無理なく使う収納例
家具と家具の間、あるいは冷蔵庫と壁の間など、お部屋にはどうしても中途端端な「すき間」が生まれがち。こうしたわずかなスペースも、工夫次第で便利な収納場所として活用できることがあります。
例えば、幅が狭く、奥行きのあるワゴンや棚などは、こうしたすき間に収まりやすく作られているものもあります。
ただし、すき間を無理に物で埋めようとすると、かえって圧迫感が出たり、風通しが悪くなって湿気やホコリが溜まる原因になったりすることも考えられます。
まずは、そこに本当に収納が必要かを冷静に考えることが大切です。
もし収納を設ける場合は、ほこりが溜まらないようにお掃除のしやすさ(例えば、キャスター付きで簡単に動かせるかなど)も考慮して、無理のない範囲で活用しましょう。
用途に合わせて置き場所を決めるコツ
物がなかなか片付かない、使った後につい出しっぱなしにしてしまう。
もしそう感じることがあれば、その物の「置き場所」が、実際の暮らし方に合っていないのかもしれません。
収納場所を決める一番のコツは、「どこで使うか」を基準に考えることです。
例えば、お手紙や公的な書類を確認する場所がいつもリビングのテーブルなら、開封に使う文具(はさみやカッター)や、一時的に保管するファイルも、リビングのテーブルの近くに置くのが自然な流れです。
玄関で使う鍵や印鑑、宅配便の受け取りに使うペンなどを、わざわざ別の部屋に取りに行くのは手間がかかります。
これらは玄関の小さな引き出しやトレイに置き場所を作ると、探す手間が省け、使った後もすぐに戻せます。
このように、ある一連の行動(例えば「洗濯」なら、洗剤、ハンガー、洗濯ネット)で使うものをひとまとめにし、それを使う場所の近くに収納する「グルーピング」という考え方を意識すると、物の「住所」が明確になり、家事や身支度がスムーズになります。
まとめ

「見せる収納」と「隠す収納」には、それぞれ異なる良さがあり、どちらか一方が正しいというわけではありません。
部屋をすっきりと見せたい、生活感を抑えたいときには「隠す収納」が役立ちますし、お気に入りのものやよく使うものは「見せる収納」にすることで、暮らしが楽しく便利になります。
収納スタイルを使い分けるポイント
収納を考えることは、自身やご家族が「今、どんな暮らしをしたいか」を見つめ直すことでもあります。
大切なのは、すべての場所を完璧に整えることよりも、そこで過ごすご自身が「心地よい」と感じるバランスを見つけることです。
ある人にとっては快適な収納が、別の人にとっては使いにくいこともあります。また、ライフスタイル(生活様式)が変われば、快適な収納の形も変わっていきます。
一度決めた方法がしっくりこなくなったら、それは暮らし方が変わったサインかもしれません。
その都度、置き場所やしまい方を気軽に見直しながら、今の自分に合った、無理のない整った暮らしを育んでいきましょう。