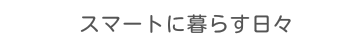季節の変わり目が近づくと、クローゼットやタンスの中を思い浮かべて、「そろそろ衣替えをしなくては…」と、少し気が重くなってしまうことはありませんか。
「時間も手間もかかりそう」「どこから手をつければいいか分からない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。特に忙しい毎日の中では、衣類の入れ替えは後回しにしてしまいがちです。
けれど、衣替えは単に服を入れ替える作業というだけでなく、ご自身の持ち物を見直し、次の季節を心地よく迎えるための大切な準備の時間でもあります。
この記事では、そんな衣替えの負担を少しでも軽くし、スムーズに進めるための具体的な「準備の段取り」や「衣類の見直しのコツ」、そして大切な服を長持ちさせる「保管の方法」などを、順を追って丁寧にご紹介します。
毎年の恒例作業を、暮らしを整える前向きな時間に変えていきましょう。
季節の入れ替えをスムーズにする準備と段取り

衣替えをスムーズに終えるには、何よりも「準備」と「段取り」が大切。
行き当たりばったりで始めてしまうと、途中で服が山積みになってしまったり、思った以上に時間がかかってしまったりすることも。
まずは、「いつ」「どこで」「どのように」進めるかを、自身のペースに合わせて決めておくことから始めましょう。
衣替えのタイミングを見極めるコツ
衣替えを始めるタイミングは、悩みがちなポイントのひとつですよね。
早すぎてもまだ着る服をしまってしまったり、遅すぎると急な気温の変化に対応できなかったりします。
一般的には、日々の「最高気温」を目安にすると分かりやすいでしょう。
例えば、春から夏にかけての衣替え(長袖や厚手の服をしまい、半袖を出す)は、日中の最高気温が20度や25度を安定して超える日が続いた頃がひとつの目安になります。この頃になると、アウターや厚手のニットを着る機会がぐっと減ってきます。
逆に、秋から冬にかけての衣替え(半袖をしまい、長袖やアウターを出す)は、最高気温が20度を下回り、15度に近い日が増えてきた頃が考えられます。肌寒さを感じる日が増えたら、それは冬支度のサインです。
大切なのは、天気予報の週間予報などを参考にしつつも、「一気にすべてを入れ替えない」こと。
特に季節の変わり目は、日によって気温差が大きい「三寒四温」のような時期もあります。
まずは使用頻度の低い服(真夏に着る薄手の服や、真冬に着る厚手のコートなど)から入れ替えを始め、中間着(カーディガンや薄手の長袖など)はすぐに出せる場所に残しておくと、気温の変化にも柔軟に対応できて安心です。
自身の体感や、お住まいの地域の気候を見ながら、「この週末は暖か(涼し)そうだから、少しずつ準備しよう」というように、無理のないタイミングを見極めてみてください。
始める前に整えておきたいスペース確認
衣替え作業を効率よく進めるためには、作業を始める前に「スペース」を確保しておくことが非常に重要です。作業スペースが狭いと、服を広げられず、分類や確認の効率が下がってしまいます。
最低でも、2つの「スペース」を確認しておきましょう。
一つは、作業を行うための「一時置きスペース」です。
クローゼットや収納ケースから出した服をすべて広げ、分類したり、状態を確認したりするための場所です。例えば、ベッドの上や、あらかじめきれいに掃除しておいたリビングの床などが適しています。
床に直接置くのが気になる場合は、清潔なシーツやレジャーシートなどを敷くとよいでしょう。このスペースが広いほど、作業は格段にはかどります。
もう一つは、これから服をしまう「収納スペース」そのもの。
まず、シーズンオフの服をしまう予定の収納ケースやタンスの引き出しは、あらかじめ中身を空っぽにしておきます。そして、底に溜まったホコリやゴミを掃除機で吸い取り、乾いた布で軽く拭き掃除をしておくと衛生的です。湿気がこもっていた場合は、少し風を通しておくと、カビやニオイの予防にもつながります。
同時に、次のシーズンの服を入れるクローゼットやタンスも、どのあたりに何を入れるか、ある程度配置を想像しておくと、作業が止まらずに進みます。
短時間で進めるスケジュールの立て方
衣替えを「一日で全部終わらせないと」と思うと、一大決心が必要になり、なかなか取りかかれない原因にもなってしまいます。
もし時間が限られている場合や、体力的に不安がある場合は、決して無理をせず「今日はここまで」と決めて、数日に分けて進めるのが賢明です。
ご自身の暮らしのリズムに合わせて、負担の少ない小さなスケジュールを立ててみましょう。
例えば、以下のような分け方があります。
- 「しまう作業」と「出す作業」で分ける
- 今週末は、まずシーズンオフの服を洗濯して、しまう作業だけする
- 次の週末に、次のシーズンの服を出す作業と、クローゼットの整理をする
- 「アイテムごと」に分ける
- 「今日はトップスだけ」「明日はボトムスとインナーだけ」というように、服の種類ごとに分けて進める
- 「今日はトップスだけ」「明日はボトムスとインナーだけ」というように、服の種類ごとに分けて進める
- 「場所ごと」に分ける
- 「今日はクローゼットの右側だけ」「明日はタンスの引き出し2段分だけ」というように、収納場所ごとに区切って進める
- 「今日はクローゼットの右側だけ」「明日はタンスの引き出し2段分だけ」というように、収納場所ごとに区切って進める
- 「人ごと」に分ける
- 「今日は自分の分だけ」「明日は子どもの分」というように、家族のメンバーごとに分ける
このように小さく分割することで、1回の作業時間は短くなり、隙間時間でも進められるようになります。
「今週中にすべて」ではなく「今月中にゆっくり終わらせる」くらいの気持ちで、ご自身のペースを大切にしてください。
入れ替え時に行う衣類の見直しポイント

衣替えは、クローゼットやタンスの中身をすべて一度取り出す、絶好の機会です。
ただ服を入れ替えるだけでなく、「本当にこの服は、次の季節も着るかな?」と、ご自身の持ち物と向き合う“プチ整理”の時間にしてみましょう。
着ない服を判断するシンプルな基準
収納スペースには限りがありますよね。
服を見直すときは、あまり深く悩みすぎず、ご自身なりのシンプルな基準で「要」「不要」「保留」を判断するのがコツです。
例えば、以下のような基準で、1枚ずつ手に取って確認してみましょう。
- 着用頻度の基準
- この1年(または2年)の間に、一度でも着る機会があったか
- もし着ていない場合、その理由は何かを考えてみましょう
- 状態の基準
- 汚れ、シミ、黄ばみ、毛玉、虫食い、ほつれなど、目立つ傷みはないか
- 生地が擦り切れたり、ヨレヨレになったりしていないか
- サイズ・好みの基準
- 今の自分のサイズや体型に合っているか(窮屈さや、だらしなさはないか)
- デザインや色が、今の自分の好みや雰囲気に合っているか
- 着てみて、心地よいと感じるか、気分が上がるか
- ライフスタイルの基準
- 今の自分の暮らし(仕事、子育て、趣味など)の場面で、着る機会があるか
- お手入れ(洗濯やアイロンがけ)が、自分にとって面倒すぎないか
- 重複の基準
- よく似たデザインや色の服が、他にもないか
これらの基準に照らし合わせて、「まだ着たい服(=しまう服)」「少し考える服(=保留)」「手放す服」というように、大まかに3つに分けてみましょう。
一時保管・寄付・リユースの使い分け
「手放す服」と判断したものでも、その方法はいくつかあります。
また、「迷う服」の扱いも決めておくと、整理が進みます。
- 一時保管(保留ボックス)
- 「今は着ないけれど、手放す決心がつかない」「サイズが変わったら、また着るかもしれない」という服は、「一時保管ボックス」のようなものを作って、そこに入れておく
- ただし、「次の衣替えの時まで」というように期限を決めておくことが大切です。期限が来たら、もう一度見直す
- 寄付・リユース(再利用)
- まだきれいな状態で、誰かに使ってもらえそうなものは、寄付やリユースの仕組みを活用するのも一つの方法
- 住まいの地域で行われているリサイクル活動や、衣類を回収している施設、または専門のショップなどを調べてみる
- 清掃用などへの再利用
- 汚れや傷みがひどい綿素材のTシャツなどは、小さく切って掃除用の布として使い切るという方法もあります
大切なのは、ご自身が納得して「ありがとう」の気持ちで手放せる方法を選ぶことです。
衣替えのたびに減らす“プチ整理”の習慣
衣替えのたびにこうした見直しを習慣にすると、手持ちの服の量が少しずつ適正になっていきます。
「自分は今、どんな服をどれくらい持っているか」を把握できるようになると、衣替えの作業そのものも時間短縮につながります。
また、「いつもこのタイプの服は着ないで手放しているな」「この色の服はよく着ているな」というご自身の傾向が分かり、次のお買い物の参考にもなります。
こうすることで、衝動的な買い物を減らし、本当に必要なものだけを選ぶ目を養うことにもつながります。
衣替えを、単なる入れ替え作業ではなく、暮らしをより快適にするための“整理の習慣”として取り入れてみてくださいね。
シーズンオフの衣類を長持ちさせる保管法

次の季節まで、大切な衣類を良い状態で保つためには、しまう前の「ひと手間」と「保管の方法」がとても重要です。
これを怠ってしまうと、次の季節に出したときに「黄ばんでいた」「虫に食われていた」という残念なことになりかねません。
湿気・虫・ニオイを防ぐ保管環境の整え方
シーズンオフの衣類をしまう前には、必ず洗濯やクリーニングで「汚れ」を完全に落としておくことが、最も大切なポイントです。
目に見えない皮脂汚れや、わずかな食べこぼしのシミなどが、保管中に黄ばみやカビ、虫食い、ニオイの原因になることがあります。
「一度しか着ていないから」と思っても、長期間しまう前には、もう一度洗濯(「しまい洗い」とも呼ばれます)をしておくと安心です。
洗濯した衣類は、湿気が残らないように、天気の良い日によく乾かしてからしまいましょう。生乾きはカビの最大の原因になります。
収納ケースやクローゼットには、市販されている防虫や防湿のためのアイテムを一緒に入れておくと、より安心です。
防虫アイテムは、衣類の上に置くと成分が下に広がりやすいとされています。使用期限が切れると効果がなくなってしまうため、いつ入れたか日付を書いて貼っておくと、次の入れ替え時の目安になります。
そして、衣類を収納ケースに詰め込みすぎないことも、風通しを良くするために重要です。ぎゅうぎゅうに詰め込むと、湿気がこもりやすくなるだけでなく、シワの原因にもなります。
クリーニング後のしまい方のコツ
クリーニングから戻ってきた衣類は、そのままクローゼットにしまいがちです。
ですが、かかっているビニールのカバーは、基本的にはクリーニング店からの輸送や、一時的なほこりよけのためのものであることが多いです。
このビニールをかけたまま長期間保管すると、通気性が悪いため、カバーの内側に湿気がこもりやすくなる可能性があります。また、クリーニングの溶剤がわずかに残っている場合、それがニオイや変色の原因になることも考えられます。
しまう前には、ビニールカバーは必ず外し、数時間ほど風通しの良い場所で陰干しをして、湿気や溶剤のニオイを飛ばしてから保管するのがよいでしょう。
その後、ほこりを防ぎたい場合は、通気性の良い不織布(ふしょくふ)で作られた衣類カバーなどにかけ替えることを検討しましょう。
※クリーニング店によっては、そのまま保管できる専用の通気性カバーを提供している場合もあります
次の季節にすぐ使える収納準備
「あのセーターは、どのケースにしまったかな?」と、次の季節に探す手間を省く工夫も、衣替えをラクにする大切なポイントです。
- ラベリングをする
- 収納ケースや引き出しには、中身が分かるラベルを貼っておくと一目でわかります
- 「セーター類」「夏物Tシャツ」「〇〇(家族の名前)の冬服」というように、分かりやすい言葉で書いておきましょう。マスキングテープやシールなどを活用すると、簡単です。
- 中身のリスト(目録)を作る
- 特に中身が見えないケースの場合は、入っているもののリストを紙に書いて、ケースの側面に貼っておくのもおすすめです
- 特に中身が見えないケースの場合は、入っているもののリストを紙に書いて、ケースの側面に貼っておくのもおすすめです
- 透明・半透明のケースを選ぶ
- 中身がうっすらと見えるタイプの収納ケースを選ぶと、開けなくても何が入っているか把握しやすいです
- 中身がうっすらと見えるタイプの収納ケースを選ぶと、開けなくても何が入っているか把握しやすいです
- しまう順番を工夫する
- 特によく着る服や、次のシーズンに最初に着たい服(薄手の羽織ものなど)は、取り出しやすい手前や上に置くなど、しまう順番を工夫すると使いやすいです
家族で協力して行う衣替えの工夫

ご家族の人数が多ければ多いほど、衣替えの作業量は増えてしまいます。
一人だけがすべてを抱え込むのではなく、家族みんなで協力できる仕組みを作ってみましょう。
子どもと一緒に進める分担方法
小さなお子さんでも、衣替えは一緒に行える作業です。
「自分の服」という意識を持ち、服を大切にする心を育むきっかけにもなります。
年齢に合わせて、簡単な作業をお願いしてみましょう。
- 幼児期(できる・できないの判断)
- 「この服、まだ着られるかな?」「小さくなっていないかな?」と一緒に服を体に当てて確認したり、「これは夏(冬)の服かな?」と仕分けを手伝ってもらったりします。
- 「この服、まだ着られるかな?」「小さくなっていないかな?」と一緒に服を体に当てて確認したり、「これは夏(冬)の服かな?」と仕分けを手伝ってもらったりします。
- 児童期(たたむ・運ぶ・しまう)
- 「自分の服をたたんでみよう」「あっちのケースに運んでくれる?」「自分の引き出しにしまってみよう」と、具体的な作業を任せてみます。
最初は上手にできなくても、「ありがとう、助かったよ」と声をかけることで、達成感やお手伝いする楽しさを感じてもらえるとよいですね。
家族で共有する収納ルールづくり
家族みんなが自分で服の管理ができるようになると、衣替えだけでなく、日々の暮らしもスムーズになります。
そのためには、「誰の服が」「どこに」「どのように」入っているかが分かる、シンプルな収納ルールを決めることが大切です。
- 定位置を決める
- 「パパの靴下は、この引き出し」「〇〇ちゃんのTシャツは、ここの棚」というように、アイテムごと、人ごとに定位置(決まった場所)を決めます
- 「パパの靴下は、この引き出し」「〇〇ちゃんのTシャツは、ここの棚」というように、アイテムごと、人ごとに定位置(決まった場所)を決めます
- 分かりやすくラベリングする
- 定位置が決まったら、誰でも分かるようにラベリングをします。
- 文字が読めない小さなお子さん用には、服や靴下の「絵」や「写真」をシールにして貼ると分かりやすいです
- 出し入れしやすい場所を意識する
- 家族が自分で出し入れしやすい場所(それぞれの目線の高さや、動きやすい動線など)を意識して、収納場所を決めると、ルールが長続きしやすくなります。
- 例えば、子ども服は、お子さん自身の手が届く低い位置に収納するのが基本です
一度決めたルールも、家族の成長やライフスタイルの変化に合わせて、時々見直していくとよいでしょう。
まとめ|衣替えを“行事化”してラクに続ける

衣替えは、単なる面倒な作業ではなく、季節の移り変わりを感じ、自身や家族の暮らしを整えるための大切な時間です。
毎年の仕組みにして迷わない
衣替えを「いつ・何を・どのように」行うか、家庭でのルールを一度決めておくと、翌年からは迷わずスムーズに進められます。
作業の手順や、見直しの基準などをメモしておいたり、使う道具(収納ケースや防虫アイテムの種類・数など)をリスト化しておいたりするのもよい方法です。
「去年は防虫剤が足りなくなったから、今年は少し多めに準備しておこう」など、去年の反省点をメモに残しておくと、さらに効率が上がります。
このように、毎年の“行事”として仕組み化することで、「やらなければ」という心の負担も軽くなります。
気候の変化を楽しみながら整える暮らしへ
クローゼットやタンスの中がスッキリと片付くと、心も不思議と整うものです。
シワなくきれいにたたまれた服や、整然と並んだハンガーを見ると、とても清々しい気持ちになります。
「次の季節は、この服を着てどこへ行こうかな」
「新しく迎える季節も、心地よく過ごせそう」
そんな風に、次の季節の訪れを想像しながら行う衣替えは、新しい季節を迎えるための前向きな準備にもなります。
気候の変化を楽しみながら、ご自身のペースで、暮らしを整える習慣を続けていきましょう。