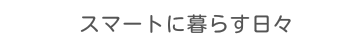お部屋をスッキリさせたいと思ったとき、「まずは収納グッズを探さなくては」と考えてしまうことはありませんか。
もちろん、便利なアイテムはたくさんありますが、一方で「グッズを買ったのに、かえって物が増えてしまった」「家のスペースに合わなかった」という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
片付けは、必ずしも新しい収納用品を必要とするわけではありません。大切なのは、今ある空間や、すでにお持ちの物を上手に活かす「工夫」と「考え方」です。
この記事では、収納グッズをむやみに増やさず、ご自宅にある空間や持ち物を使ってお部屋を整えるための、基本的な整理の考え方や具体的なアイデア、そしてそれを維持するための習慣づくりについて、丁寧にご紹介します。
収納グッズを増やさない片付けの基本

お部屋が片付いた状態を保つためには、まず基本的な考え方を知ることが大切です。
新しい収納用品に頼る前に、ご自身の持ち物や、もののしまい方についての「土台」を整えてみましょう。
使っていない物の把握から始める
片付けと聞くと「収納すること」をイメージしがちですが、その前に欠かせないのが「今、何を持っているか」を正確に把握することです。
なぜなら、管理できる以上のものがあると、どんな収納を使っても「片付かない」と感じやすくなってしまうからです。
まずは、無理のない範囲、例えば「ひとつの引き出し」「洗面台の下だけ」など、小さなスペースからで構いません。一度、中にあるものをすべて出してみましょう。
すべてを出すことで、「こんなものがあったんだ」「同じものがいくつも出てきた」といった気づきがあります。
そして、一つひとつを手に取り、「これは今の暮らしに必要か」「1年間、使っただろうか」と、ご自身の基準でゆっくりと見直してみてください。
すぐに判断できないものは、「保留ボックス」のような箱にとりあえず分けておき、一定期間(例えば3ヶ月など)を置いてから再度考えると、判断しやすくなることもあります。
この「把握」の作業こそが、収納グッズを増やす前にすべき最も大切なステップです。
収納より“出し入れしやすさ”を優先する
せっかく収納しても、取り出すのが面倒だったり、元に戻すのが難しかったりすると、使うのが億劫になったり、出しっぱなしの原因になったりします。
見た目の美しさや、隙間なく詰め込むこと(収納量)だけを優先するのではなく、「使うときの動作」や「戻すときの動作」を一番に考えてみましょう。
特に、毎日使うもの(例えば、キッチンツールや洗面用具、よく着る服など)は、できるだけ簡単な動作で出し入れできる場所が理想です。
一般的に、人の目線から腰の高さまでの範囲は「ゴールデンゾーン」とも呼ばれ、最も作業がしやすい場所とされています。こうした場所に、使用頻度が最も高いものを配置するのがコツです。
逆に、年に数回しか使わないものは、少し取り出しにくい場所(例えば、棚の上段や奥まった場所)でも構いません。
「使用頻度」を軸にして置き場所を決めていくと、自然と日常の動作がスムーズになり、散らかりにくい仕組みが整っていきます。
家にある物を活用した整理の工夫
引き出しの中を仕切りたい、小物をまとめたいと思ったとき、すぐに新しい仕切りケースを探す前に、家庭にあるものを活用できないか考えてみましょう。
例えば、お菓子や食品が入っていたしっかりした作りの「空き箱」は、引き出しの中の仕切りとして十分役立ちます。高さが合わない場合は、箱の上部をカッターなどでカットして調整することもできます。
また、使わなくなった「クリアファイル」は、書類を立てて収納する際の仕切り板代わりにしたり、衣類を立てて収納する際の芯として使ったりすることもできます。
ほかにも、ジャムなどの「空き瓶」は、文房具や細かなキッチンツールを立てて見せる収納に使えますし、丈夫な「紙袋」は、持ち手を内側に折り込めば、野菜室の整理や棚の上の軽いものをまとめる箱代わりになります。
もちろん、見た目の統一感を大切にしたい場合は、色を揃えたり、同じ形の箱を集めたりといった工夫も楽しめます。
まずは身の回りを見渡して、上手に再利用できるものがないか探してみるのも良いですね。
スペースを活かす収納アイデア

お部屋を見渡したとき、一見すると「もう収納する場所がない」と感じるかもしれません。しかし、視点を変えてみると、まだ活用できるスペースが隠れていることがよくあります。
棚や引き出しの“空き”を見直す
棚や引き出しの中は、ぎっしりと詰まっていませんか?
ものが詰まりすぎていると、奥にあるものが分からなくなったり、取り出すために手前のものを一度どかさなければならなかったり、と手間が増えてしまいます。
収納スペースには、ある程度の「空き(余白)」を持たせることが大切です。
よく「収納は8割程度に」と言われることがありますが、これは空間にゆとりを持たせることで、ものの出し入れをしやすくするだけでなく、何がどこにどれだけあるかを一目で把握しやすくするためです。
在庫管理がしやすくなれば、同じものを二重に買ってしまうことも防ぎやすくなります。
また、空間にゆとりがあれば空気の通り道もできるため、特に衣類や食品を扱う場所では、湿気やカビの対策という観点からも意味があります。
まずは、今ある収納スペースに少し「空き」をつくることを意識してみましょう。
家具まわりの“すき間”を活かす収納
家具と家具の間、家具と壁の間など、お部屋には小さな「すき間」がたくさんあります。こうしたデッドスペース(有効活用されていない空間)も、工夫次第で収納場所として活かせる場合があります。
例えば、冷蔵庫と壁の間のわずかなすき間、洗濯機と洗面台の間のすき間、あるいはソファやベッドの下の空間などです。
ただし、こうした場所にものを置く場合は、いくつか注意が必要です。
まず、「お掃除の邪魔にならないか」という点です。ものを置いたことで掃除機がかけにくくなり、かえってホコリが溜まる原因になっては本末転倒です。キャスター付きの台に乗せるなど、簡単に移動できる工夫をすると良いでしょう。
また、地震などの際に「倒れたり、落ちたりしないか」という安全性も必ず確認してください。
無理に詰め込むのではなく、あくまで「安全」と「清潔さ」を保てる範囲で、小さなスペースにも目を向けてみましょう。
一時置き場を決めて散らかりを防ぐ
「すぐに片付けられないもの」は、誰の家にもあるはずです。例えば、届いたばかりの郵便物、後で読もうと思っている新聞や雑誌、まだカバンに戻していないお財布や鍵などです。
こうした「行き場のないもの」が、テーブルやカウンターの上にとりあえず置かれ、そのまま散らかって見える原因になることは少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、「一時置き場」を明確に決めておくことです。
玄関先やリビングの一角に、お気に入りの「トレイ」や「カゴ」を一つ用意し、「家に帰ったら、鍵や郵便物はまずここに入れる」というルールを決めてみましょう。
「とりあえず」の置き場所が定まることで、お部屋のあちこちにものが点在するのを防ぐことができます。
ただし、この「一時置き場」は、あくまで「一時的」な場所です。
「週末になったら中身を空にする」「このカゴがいっぱいになったら整理する」など、定期的に中身を見直すルールも一緒に決めておくことが、上手に活用するコツです。
片付けをラクにする習慣づくり

お部屋を一度きれいにしても、それを維持できなければ、またすぐに散らかってしまいます。大切なのは、頑張りすぎなくても自然と片付いた状態が続く「仕組み」と「習慣」です。
「使ったら戻す」を家族で共有する
片付けの最も基本的で、最も大切な習慣が「使ったら、元の場所に戻す」ことです。
これができていれば、部屋がひどく散らかることはありません。しかし、このシンプルな習慣が案外難しいもの。
特にご家族など、一緒に暮らす人がいる場合は、「どこに何があるか」という「ものの定位置」を全員が知っていることが重要です。
「お母さんしか分からない」という状態では、他の人は戻しようがありません。
まずは、「誰でも分かる」仕組みづくりを意識しましょう。例えば、引き出しや箱に中身が分かるような簡単な「ラベリング」をするのも良い方法です。(例:「文房具」「救急セット」など)
また、その「定位置」が、本当に戻しやすい場所になっているかも見直してみましょう。フタを開けて、箱をどけて、ようやく戻せる…というように動作が多い(アクション数が多い)と、戻すのが面倒になってしまいます。
できるだけ少ない動作で戻せるよう、収納方法自体をシンプルにすることも大切です。
家族みんなで「ここが一番使いやすいね」と話し合って場所を決めるのも良いですね。
片付けの“ついで習慣”を取り入れる
「よし、今から片付けよう」と意気込むと、時間も気力も必要になり、なかなか行動に移せないことがあります。
そこでおすすめなのが、「何かのついで」に小さな片付けを組み込む「ついで習慣」です。
例えば、「朝、顔を洗うついでに、洗面台の鏡をさっと拭く」「お茶を淹れるついでに、コンロ周りを拭き掃除する」「テレビを見ているCMの間に、テーブルの上だけ整える」「お風呂に入るついでに、排水溝の髪の毛を取る」「部屋を移動するついでに、リビングに置きっぱなしのコップをキッチンへ持っていく」。
このように、日常の決まった動作に「プラスワン」の小さな片付けをセットにするのです。
一つひとつは1分もかからないような小さなことでも、これが習慣になれば、汚れや散らかりが溜まるのを防ぐことができます。
「頑張って片付ける」のではなく、「暮らしの中に自然に溶け込ませる」という意識が、ラクに続けるコツです。
新しい物を増やす前にスペースを確認する
ものが増え続けると、いくら整理や収納を工夫しても、いつかは限界が来てしまいます。お部屋をスッキリと保つためには、「入り口(ものを増やすこと)」にも意識を向けることが大切です。
新しく何かものを迎え入れたいと感じたときは、すぐに買うのではなく、一度立ち止まって「それを本当に置くスペースがあるか」をご自宅の収納と相談してみましょう。
「あの棚の、あの空いている場所に置こう」と、具体的な置き場所までイメージできてから購入する癖をつけると、衝動買いや、「買ったはいいけど置き場所がない」といった事態を防ぎやすくなります。
また、「一つ買ったら、一つ見直す(手放す)」という考え方(ワンイン・ワンアウトと呼ばれることもあります)を取り入れるのも一つの方法です。
これにより、ご自宅のものの総量が無尽蔵に増えるのを防ぐことができます。
新しいものを買う前に、今あるものとしっかり向き合う習慣を持つことが、収納グッズを増やさない暮らしへの近道です。
まとめ|あるもので整える心地よい暮らしへ

収納グッズを新しく増やさなくても、今ある空間や持ち物を活かして、お部屋を心地よく整えるための工夫や考え方をご紹介しました。
収納グッズを増やせずにスッキリ保つコツ
大切なポイントは、まずご自身の持ち物を「把握する」ことから始めること。
そして、見た目や収納量よりも「出し入れのしやすさ」を優先して、ものの定位置を決めることです。
今ある棚や引き出しに「空き(ゆとり)」を持たせること、そして家具まわりの「すき間」など、これまで見過ごしていたスペースに目を向けてみることも有効なアイデアです。
こうした工夫と、「使ったら戻す」「ついでに片付ける」といった日々の小さな習慣が組み合わさることで、お部屋はスッキリとした状態を保ちやすくなります。
無理なく続けられる整理の仕組みをつくる
片付けは、一度きりの「イベント」ではありません。日々の暮らしの中で続いていくものです。だからこそ、完璧を目指して頑張りすぎるのではなく、ご自身やご家族が「無理なく続けられる」ことが何よりも大切です。
収納グッズに頼る前に、まずは「今あるもの」で、どうしたらもっと快適に暮らせるかを考えてみませんか?
その上で少しずつ「我が家にとっての心地よい仕組み」をつくっていきましょう。