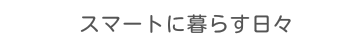毎日の食事の準備や後片付けに、なんとなく時間がかかっていると感じることはありませんか。
食器棚はいっぱいなのに、よく使うお皿はいつも手前の数枚だけ。奥にある食器は取り出しにくく、いつの間にか存在を忘れてしまっている…。
そんな日常の小さなモヤモヤは、もしかすると食器の「量」が関係しているかもしれません。
食器を減らすと聞くと、「お客様が来たときに困るかも」「種類が少ないと食卓が寂しくなるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、大切なのは「ただ数を減らす」ことではなく、「ご自身やご家族にとって本当に使いやすい食器を厳選する」ことです。
この記事では、無理なく食器を見直し、家事がスムーズになるキッチンを作るためのシンプルな工夫や考え方を、ステップに分けて詳しくご紹介します。
管理する食器が減ることで生まれる、心のゆとりや時間の余裕を感じてみませんか。
食器を減らすと家事がスムーズになる仕組み

食器の数を厳選することには、見た目のスッキリさ以外にも、毎日の家事を効率化するための多くの利点があるといわれます。
まずは、食器を減らすことで家事の流れがどのようにスムーズになるのか、その具体的な仕組みについて見ていきましょう。
洗い物・片付け・収納が一連でラクになる
食器の総量が減ると、まず変化を感じやすいのが「洗い物」です。
シンクに置かれる食器や、食洗機に入れる食器の数が物理的に減るため、一度に洗う手間と時間が短縮されます。
洗い終わった後、水切りカゴがいっぱいになって作業が中断することも少なくなるでしょう。拭き上げの作業もスムーズに進みます。
さらに大きな変化は「片付け」と「収納」です。食器棚に戻す際、どこに何をしまうかが一目瞭然になります。収納スペースに「余白」が生まれるため、食器同士がぶつかることなく、ゆとりを持って配置できます。
パズルのように詰め込む必要がなくなり、片付けの動作そのものがとてもシンプルで楽になります。
動線が整うことで作業効率がアップする
キッチンでの作業効率を考える上で、「動線(どうせん)」はとても大切です。動線とは、キッチンの中で人が移動する軌跡(通る道筋)のことを指します。
例えば、調理中を想像してみてください。「冷蔵庫から食材を出す」「シンクで洗う」「調理台で切る」「コンロで加熱する」「食器棚からお皿を出す」「盛り付ける」。
この一連の流れがスムーズにつながることが理想です。
もし食器棚がいっぱいで、使いたいお皿を探すのに時間がかかると、そのたびに調理の手が止まってしまいます。食器の数が厳選されていれば、迷わずサッと取り出せるため、調理から配膳、後片付けまでの流れが途切れません。
キッチン内を何度も往復したり、探し物をしたりする時間が減ることで、作業効率は自然と上がっていきます。
探し物が減り、ストレスも軽減される
「あのお皿はどこだっけ?」「重ねたお皿の下にあって取り出せない…」
こうした探し物や取り出しにくさは、私たちが思っている以上に小さなストレスを心に与えています。使いたいものがすぐに見つからない状況が続くと、家事そのものが億劫に感じてしまう原因にもなりかねません。
食器の数を減らし、食器棚全体を見渡せる状態(一覧できる状態)にすると、探し物をする機会が劇的に減ります。
どこに何があるかを把握できているという安心感は、気持ちの負担を軽くし、毎日のキッチン仕事を前向きなものに変えてくれるでしょう。
キッチンを軽やかに保つための減らし方ステップ

食器を減らすといっても、いきなりすべてを見直すのは大変です。何から手をつければよいか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、ご自身のペースで無理なくキッチンを整えるための、基本的な3つのステップをご紹介します。
「使う頻度」で仕分けしていく
まずは、今お持ちの食器を「どのくらいの頻度で使っているか」という基準で仕分けしてみましょう。
- 全部出してみる
まずは食器棚や引き出しから、すべての食器を取り出してみます。持っている量を把握することが第一歩です。 - グループに分ける
次に、使用頻度ごとに4つのグループに分けてみましょう。- 【1軍】毎日、または週に数回かならず使う(例:ごはん茶碗、汁椀、メインのお皿)
- 【2軍】週に1回程度、または特定の料理で使う(例:麺鉢、カレー皿)
- 【3軍】月に数回、または季節行事などで使う(例:グラタン皿、来客用)
- 【4軍】ここ1年以上、ほとんど使っていない
仕分けをすることで、ご自身にとって本当に必要な食器と、そうでない食器がはっきりと見えてきます。
まずは「4軍」の食器から、なぜ使わなくなったのか(重い、洗いにくい、好みでなくなった等)を考え、手放すことを検討してみるのが、負担の少ない始め方です。
セット食器より単品を選んで調整しやすく
セットでそろえた食器は、食卓に統一感が出るという利点があります。しかし一方で、一部が欠けたり割れたりした時に、残りの食器の出番も一緒に減ってしまうことがあります。
5客セットのうち1客だけ割れてしまい、4客では使いにくく、結局しまい込んだまま…というケースも少なくありません。
もしこれから食器をそろえる場合や、買い替えを検討する場合は、単品で選ぶ方法も視野に入れてみましょう。家族の人数やライフスタイルの変化に合わせて、1枚ずつ買い足したり、減したりすることができます。
デザインがシンプルで、和食にも洋食にも合わせやすいものを選んでおくと、手持ちの他の食器とも組み合わせやすく、活用の幅が広がります。
一日一か所だけ見直す“ながら整理”法
食器棚全体を一度に整理しようとすると、時間も労力もかかり、途中で挫折してしまう原因になります。大切なのは、完璧を目指すことよりも、小さな範囲でいいので「続ける」ことです。
そこでおすすめなのが、「一日一か所だけ」と決めて見直す“ながら整理”法です。
例えば、「今日はカトラリーの引き出しだけ」「明日はグラスを置いている棚だけ」というように、ごく小さな範囲に限定します。
夕食後の片付けが終わったついでに5分だけ、お茶を淹れるお湯を沸かしている合間に少しだけ、といった「ながら時間」を活用してみましょう。
この方法なら、まとまった時間を取る必要がなく、精神的なハードルも下がります。小さな達成感を積み重ねることが、整理整頓を習慣化する一番の近道です。
暮らしをラクにする食器の選び方

食器を減らしてスッキリした状態を維持するためには、新しく迎える食器の「選び方」も非常に重要になります。
ここでは、少ない食器で快適に、そして効率よく暮らすための選び方のポイントを見ていきましょう。
形とサイズをそろえて収納しやすく
食器棚をスッキリと見せるコツは、食器の「形」と「サイズ」をある程度そろえることです。 形や大きさがバラバラだと、収納したときにデッドスペース(無駄な空間)が生まれやすくなります。
例えば、毎日使うメインのお皿は「直径23cmの丸皿」、取り皿は「直径15cmの丸皿」というように、基本的なサイズを決めておくと、重ねたときにきれいにそろい、見た目も美しくなります。
特にこだわりがなければ、丸皿は収納効率が高く、洗いやすい形といえます。もし角皿を選ぶ場合も、できるだけ同じ大きさや形でそろえると、重ねやすくなります。
ご自宅の食器棚の奥行きや高さをあらかじめ測っておき、それに合うサイズを選ぶことも大切です。
重ねやすいデザインで省スペース化
食器棚のスペースは限られています。特に日本のキッチンスペースでは、いかに効率よく収納するかが課題になることも多いでしょう。
食器を選ぶ際には、きれいに重ねられるかどうか、つまり「スタッキング性能」を確認してみましょう。スタッキングとは、積み重ねることを意味します。
食器の裏側にある「高台(こうだい)」と呼ばれる出っ張りが高すぎたり、フチのデザインが個性的すぎたりすると、うまく重ねられずにかさばってしまいます。
できるだけフチがシンプルで、高台が低いデザインを選ぶと、同じ高さのスペースにより多くの枚数を収納できます。
お店で選ぶ際には、実際に同じ食器を2〜3枚重ねてみて、安定感や高さを確認してみるのもよい方法です。
お気に入りを少数だけ残して長く使う
食器の数が少なくなると、一つひとつの食器を使う頻度は自然と高くなります。だからこそ、デザインや使い心地など、ご自身の基準で「心から気に入ったもの」を選ぶことが大切です。
数が少なくても、お気に入りの食器に囲まれていれば、毎日の食卓は豊かで満足度の高いものになります。
「なんとなく」で選んだ食器をたくさん持つよりも、「これだ」と思えるものを少数だけ選び、大切に長く使い続ける。そんな姿勢が、シンプルな暮らしと、モノを大切にする心につながっていきます。
ご自身にとっての「お気に入り」の基準(例:手触りが良い、料理が映える色、洗いやすい軽さなど)を明確にしておくと、新しい食器を選ぶ際にも迷いが少なくなります。
片付けやすいキッチンを保つコツ

食器を減らしてスッキリした状態を手に入れても、それを維持できなければ意味がありません。大切なのは、日々の小さな習慣によって「散らかりにくい仕組み」を作ることです。
ここでは、片付けやすいキッチンを保つための3つのコツをご紹介します。
使ったら戻すを徹底する「1アクション収納」
片付けが面倒になる一番の原因は、元の場所に戻すまでの「動作(アクション)」が多すぎることです。
例えば、食器をしまうのに、「①扉を開ける → ②手前の物をどかす → ③奥の箱を取り出す → ④箱のフタを開ける → ⑤食器をしまう」というように5つも動作が必要だと、戻すのが億劫になり、つい出しっぱなしにしてしまいます。
理想は「1アクション」、多くても「2アクション」でしまえる収納です。
「扉を開けるだけ」「引き出しを引くだけ」で、目的の場所にサッと戻せる仕組みを作りましょう。
そのためには、使用頻度に合わせて収納場所を工夫することが大切です。毎日使う1軍の食器は、目線から腰の高さまでの、一番取り出しやすい「ゴールデンゾーン」に配置するのが基本です。
1日5分のリセット習慣でリバウンド防止
一度きれいに片付けても、数日経つとまた元の散らかった状態に戻ってしまうことを「リバウンド」と呼びます。これを防ぐために効果的なのが、1日の終わりにキッチンを元の状態に戻す「リセット習慣」です。
時間は、たとえ5分でも構いません。大切なのは「毎日続けること」です。 「寝る前に必ずキッチンのリセットをする」と決め、例えば以下のようなことを習慣にしてみましょう。
- 調理台の上に出ている調味料などを定位置に戻す
- 調理台やテーブルの上を台拭きで拭く
- シンクの中に洗い物やゴミが残っていない状態にする
- 使った布巾などを洗って干す
この5分の習慣が、翌朝の気持ちよいスタートにつながります。汚れもその日のうちに落とすことで、大掃除の手間も省けます。
来客前に慌てない整った空間づくり
普段から食器や調理器具の定位置が決まっていると、急な来客時にも慌てることが少なくなります。
「お客様用のお皿はどこだっけ?」と食器棚の奥を探し回る必要がなくなれば、その分、おもてなしの準備に心を集中できます。
来客用の食器をどうするかは悩みどころですが、例えば「普段使いもできる、少し上質でシンプルなデザインのもの」をいくつかそろえておき、普段の食事でも使うようにすると、食器の総数を増やさずに対応できます。
もし、年に数回しか使わない特別な食器がある場合は、「普段使いの食器棚」とは別の場所(例:吊り戸棚の上段など)にまとめて保管しておくと、日常の動線を邪魔しません。
まとめ|少ない食器で家事が整う暮らしへ
食器を見直すことは、単にモノを減らすという行為だけでなく、日々の家事や、暮らし方そのものを見つめ直すきっかけにもなります。
減らすことで見えてくる“使いやすさ”
食器を厳選していく過程で、自身や家族にとっての「ちょうどよい量」や「本当に使いやすい形・重さ」が、だんだんと明確になってきます。
数が減ることで、食器棚には余白が生まれ、一つひとつの食器と丁寧に向き合う時間が増えます。
その結果、「このお皿は、実はこんな料理にも合うんだ」という新しい発見や、その食器本来の使いやすさを再認識できるかもしれません。
管理するモノが減ることは、頭の中(思考)の整理整頓にもつながり、心の軽やかさをもたらしてくれます。
無理なく続くシンプルなキッチンを目指して
大切なのは、一度に完璧を目指すことではなく、ご自身のペースで無理なく続けることです。
ご家族の状況やライフスタイルによって、「心地よい」と感じる食器の量や種類は異なります。
「減らさなくては」と焦る必要はありません。まずは「今日は引き出しを一つだけ見てみよう」という小さな一歩から始めてみませんか。
日々の暮らしの中で少しずつ工夫を重ねながら、家事がラクになり、キッチンに立つのが楽しくなるような、シンプルな暮らしを目指していきましょう。