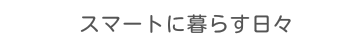子どもが生まれると、暮らしは喜びに満ち溢れる一方で、家の中の様子は一変しがちですよね。
増え続けるおもちゃや育児用品、思うように進まない家事や片付けに、ため息が出る日もあるかもしれません。
「子どもが小さいから散らかるのは仕方ない」と割り切りつつも、「もう少しスッキリとした空間で、心穏やかに暮らしたい」「家事がスムーズにまわる仕組みがほしい」と感じるのは、とても自然なことです。
大切なのは、完璧な状態を目指すことよりも、ご家族みんなが「心地よい」と感じられる、ちょうどいいバランスを見つけること。
そして、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる「仕組み」をつくることです。
この記事では、育児中でも始めやすいシンプルライフの考え方、そして家事がまわりやすくなる日常の仕組みづくりのヒントを、具体的にお伝えしていきます。
ご家庭のペースで、少しずつ心地よい暮らしを育んでみませんか。
子どもと一緒にシンプルライフを始める準備

まずは、家族みんなが快適に過ごすための「土台づくり」から見ていきましょう。
いきなり全てを変えようとせず、小さな一歩から始めることが大切です。
環境が整うと、気持ちにもゆとりが生まれやすくなりますよ。
モノを減らしすぎない“家族に合う”バランスを取る
「シンプルライフ」と聞くと、モノをとにかく減らすことを想像するかもしれません。
でも、小さなお子さんがいるご家庭では、成長に欠かせない絵本やおもちゃ、安全を守るためのベビーゲート、そして日々の暮らしを助けてくれる便利なアイテムもたくさんありますよね。
ここで大切なのは、モノの「量」にこだわりすぎず、ご家族にとって「ちょうどいい」と感じるバランスを見つけることです。生活が不便になってしまったり、窮屈に感じてしまっては、心地よい暮らしとは言えなくなってしまいます。
まずは「これは本当に今、必要かな?」「家族みんなが使いやすいかな?」「代わりになるものはないかな?」と、一つひとつのモノと向き合う時間を持ってみてはいかがでしょうか。
例えば、お子さんの安全や健やかな成長に関わるモノ、家族の時間を豊かにしてくれるモノは、無理に手放す必要はありません。
一方で、使われずにしまい込まれているモノや、「いつか使うかも」と取っておいているモノは、見直しの対象になるかもしれません。
ご家庭の状況や価値観に合わせて、必要なモノは大切に使いながら、無理のない範囲で、モノとの付き合い方を見直していくことが、心地よい暮らしへの第一歩です。
子どもの動線に合わせた収納ゾーンづくり
お子さんが自分でモノを出し入れしやすい環境づくりは、スッキリとしたお部屋を保つ上でとても大切です。
これは、お子さんの自立心を育むことにもつながります。
ポイントは、大人の目線だけでなく、お子さんの目線や動き(動線)を想像しながら収納場所(ゾーン)を作ることです。
まずは、お子さんが家の中のどこで多くの時間を過ごしているか、どこを通って移動することが多いかを観察してみましょう。
例えば、リビングでおもちゃを広げて遊ぶことが多いなら、リビングの一角におもちゃの収納ゾーンを設けるのが自然です。玄関で上着を脱ぎ着するなら、お子さんの手の届く高さに専用のフックを取り付けると、「自分でできた!」という体験につながります。
収納ゾーンを作るときは、以下の点を意識してみましょう。
- 子どもの目線や手の届く高さにする
大人が使いやすい高さではなく、お子さんが無理なく手を伸ばせる高さに設定します。 - 簡単な動作で片付けられるようにする
フタが複雑な箱や、奥まって取り出しにくい場所は避け、「投げ込むだけ」「置くだけ」といった簡単な動作で片付く工夫が役立ちます。 - どこに何を戻すか分かりやすくする
中身が見える透明なケースを使ったり、収納ボックスに写真やイラストを貼ったりすると、お子さん自身が「モノのおうち」を認識しやすくなります。
「おもちゃはここ」「お絵かきセットはあそこ」と、モノの定位置が決まっていると、お子さん自身で片付ける習慣もつきやすくなりますよ。
使う頻度で見直す「家族共用アイテム」の管理法
爪切りや体温計、耳かき、常備薬、文房具、充電ケーブルなど、家族みんなが使う共用アイテムは、あちこちに散らばってしまうと「あれ、どこだっけ?」と探す時間が増えてしまいます。
これらは、まず「どれくらいの頻度で使うものか」を基準に、置き場所を見直してみましょう。
一般的な分類としては、以下の3つが考えられます。
- 毎日使うもの(例:体温計、保湿クリーム、充電ケーブルなど)
- 週に1〜2回使うもの(例:爪切り、耳かき、特別なケア用品など)
- 月に数回か、それ以下の頻度で使うもの(例:予備の電池、あまり使わない工具類など)
このうち、「毎日使うもの」や「週に1〜2回使うもの」は、家族みんなが手に取りやすく、目につきやすい「一等地」に置くのがポイントです。
例えば、リビングの決まった引き出しや、家族が集まるテーブルの近く、キッチンのカウンターの上などが挙げられます。
あまり使わないものは、少し離れた場所(例えばクローゼットの上段や、納戸など)にまとめて保管すると、普段よく使うスペースがスッキリします。
このとき、何が入っているか分かるようにラベルを貼っておくと、いざという時に探しやすくなります。
使う頻度に合わせて置き場所を工夫するだけで、モノを探す時間がぐっと減り、家族みんなが使いやすい仕組みが整います。
育児と家事を両立しやすくする日常の仕組み

毎日を少しでもラクに、そして心穏やかに過ごすためには、根性や頑張りに頼るのではなく、無理のない「仕組み」づくりが役立ちます。
ここでは、自然と家事がまわるような流れをつくるためのヒントを見ていきましょう。
時間を区切るだけで整う1日の流れ
育児も家事も、やろうと思えば際限なくやることが出てきてしまいますよね。
特に小さなお子さんがいると、予定通りに進まないこともしばしば。
そこで試してみたいのが、「この時間はこれをやる」と大まかに時間を区切って行動する方法です。
例えば、「朝の15分はキッチンの片付けと食卓のリセット」「子どもがお昼寝したら、最初の30分は自分の休憩時間、その後30分で夕飯の下ごしらえ」といった具合です。
スマートフォンやキッチンのタイマーを使って時間を区切ると、意識が集中しやすくなります。
大切なのは、きっちり守ろうと気負いすぎないこと。
あくまでも「目安」として捉えましょう。
「この時間が目安」と意識するだけで、行動にメリハリがつき、だらだらと作業を続けてしまうことを防げます。
また、「この時間だけ頑張れば、あとは自由」と考えることで、気持ちにゆとりが生まれやすくなります。
もし計画通りにいかなくても、「今日はそんな日」と割り切ることも大切です。
まずは、ご自身の生活リズムに合わせて、短い時間から区切ってみるのが良いでしょう。
家族でシェアできるタスクの分け方
家事は、家族みんなの暮らしを支える大切なお仕事ですが、その負担がどちらか一方に偏ってしまうと、心身ともに余裕がなくなってしまいます。
「名もなき家事」という言葉があるように、実際には目に見えにくい細かなタスクもたくさんあります。
まずは、ご家庭の中にどんな家事(タスク)がどれくらいあるのかを、一度すべて書き出してみるのも一つの方法です。
「ゴミ出し」「洗濯物をたたむ」「トイレットペーパーの補充」「献立を考える」など、大小問わずリストアップしてみます。
目に見える形にすることで、家族みんなで「今、何が必要か」を共有しやすくなります。
その上で、ご家庭に合った方法でタスクを分けてみましょう。
- 得意・不得意で分ける
料理はパパ、掃除はママ、というように、お互いが比較的負担に感じない分野を担当します。 - 時間帯や曜日で分ける
平日の朝はママ、夜はパパ、週末のまとめ買いは一緒になど、生活リズムに合わせて分けます。 - 「気づいた人がやる」ルールを決める
「床に落ちたものを拾う」「使ったコップを流しに運ぶ」など、簡単なタスクは「気づいた人がやる」という共通認識を持つのも良い方法です。
大切なのは、一度決めたら変えない、ということではありません。
お子さんの成長や家族の状況に合わせて、その都度見直しながら、お互いの状況を思いやり、協力し合える体制をつくれると良いですね。
“ながら片付け”で散かりを防ぐ習慣
「あとでまとめて片付けよう」と思うと、つい後回しになりがちで、気づいた時にはお部屋が散らかってしまい、片付ける意欲も湧きにくくなる…という悪循環に陥ってしまうこともあります。
そこでおこないたいのが、“ながら片付け”。
これは、何かの「ついで」に、ほんの少しの片付けを差し込む習慣のことです。
「片付けのための時間」をわざわざ取るのではなく、日常の動作に組み込むことで、大きな散らかりを事前に防ぐことにつながります。
例えば、以下のような習慣です。
- テレビを見ながら、床に落ちているおもちゃをカゴに入れる。
- お湯を沸かしている間に、コンロ周りや調理台をさっと拭く。
- 歯を磨きながら、洗面台の鏡や水回りを軽く拭き掃除する。
- 電話で話しながら、テーブルの上の不要なチラシを片付ける。
- リビングから寝室へ移動するときに、脱ぎっぱなしの服を洗濯カゴに入れる。
一つひとつは本当に小さなことですが、これが習慣になると、家全体が「ひどく散らかった状態」になりにくくなります。
まずは、ご自身がやりやすい「ながら片付け」を一つ見つけて、意識的に続けてみることから始めてはいかがでしょうか。
子どもと一緒に片付け習慣を育てるコツ

お子さん自身の「できた!」という気持ちを大切にしながら、片付けの習慣をゆっくりと育んでいきましょう。
「片付けなさい」と指示するのではなく、大人が見本を見せながら、楽しく取り組むことが長続きの秘訣です。
焦らず、気長に見守る姿勢も大切ですよ。
子どもが片付けやすい定位置を決める
お子さんにとって「分かりやすい」こと、そして「簡単である」ことが何より大切です。
まずは、おもちゃや絵本一つひとつに「おうち(定位置)」を決めてあげましょう。
このとき、大人の都合や見た目の美しさだけでなく、お子さんの目線で決めるとうまくいきやすいです。
例えば、小さなお子さんには、細かく分類しすぎる収納よりも、ポイポイと投げ込むだけで片付くような、口の広い収納ボックスを用意するのも良いですね。
また、どこに何を入れる場所か一目でわかるようにする工夫も、お子さんの「自分でできた!」を応援します。
例えば、ボックスに中身の写真や、おもちゃの絵を描いたイラストを貼っておくのも一つの方法です。文字がまだ読めないお子さんでも、「この車の絵が描いてある箱に、車を戻せばいいんだな」と視覚的に理解できます。
「ここに戻せばいいんだ」という安心感が、片付けへの意欲につながります。
まずは、お子さんのお気に入りのおもちゃ一つからでも、「おうち」を決めてあげることから始めてみてください。
おもちゃ収納をコンパクトに保つ工夫
おもちゃは、お子さんの成長とともに自然と入れ替わっていくもの。興味の対象が移ったり、年齢に合わなくなったりすることもよくあります。
収納スペースがあふれる前に、定期的に見直す機会を持ちましょう。
一つの方法として、すべてのおもちゃを一度に出しておくのではなく、「今よく遊ぶもの」だけを厳選して出し、あまり遊んでいないものは別の場所に一時保管する、という方法もあります(ローテーション方式と呼ばれることもあります)。
こうすることで、お子さんも今あるおもちゃで集中して遊びやすくなり、片付けの量も管理しやすくなります。そして、しばらくして忘れた頃に保管していたおもちゃを出すと、新鮮な気持ちでまた遊んでくれることもあります。
また、収納スペース自体を「この棚に入るだけ」「このボックス2つ分だけ」と決めておくのも、モノが増えすぎるのを防ぐ一つのルールになります。
定期的にお子さんと一緒に「どのおもちゃで遊びたい?」「これは少しお休みしようか?」と話しながら見直すのも良いですね。
「一緒に片付ける時間」を家族行事にする
「片付けなさい!」と一方的に伝えてしまうと、お子さんにとって片付けが「やらされること」「面倒なこと」になってしまうかもしれません。
まずは、大人が楽しそうに片付ける姿を見せることが大切です。
「さあ、おもちゃをおうちに帰そうか」「ご飯の前に、みんなでスッキリさせよう」と、前向きな言葉で声をかけたり、「どっちが早くこの箱にブロックを集められるかな?」とゲーム感覚を取り入れたりするのも良いでしょう。
お気に入りの音楽をかけて、「この曲が終わるまでにお片付けしよう」と時間を区切るのも、気分転換になります。
また、「寝る前の5分間」や「ご飯の前の5分間」を「みんなでお片付けタイム」として、家族みんなで一斉に取り組むのも一つの方法です。
大人が率先して動くことで、お子さんも「自分もやろう」という気持ちになりやすくなります。
「一緒にできて助かったよ、ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることも、お子さんの自信につながりますよ。
暮らしをラクにする動線とリセットの工夫

日々の動き(動線)をスムーズにし、散らかりにくい家を保つための、ちょっとした工夫も見てみましょう。
家事の効率が上がると、時間にゆとりが生まれ、気持ちにも余裕ができます。
小さな積み重ねが、暮らしやすさにつながります。
キッチン・リビングを行き来しやすく整える
キッチンとリビングは、一日に何度も行き来する、家事の中心となる場所です。
この動線(人が移動する経路)上にモノが置かれていると、通るたびに避けたり、またいだりする必要があり、無意識のうちに小さなストレスの原因になります。
特に床にモノを直置きすることは、動線を妨げる一番の原因になりがちです。
読みかけの雑誌、お子さんのおもちゃ、脱ぎっぱなしの上着、とりあえず置いたカバンなどが床にあると、掃除機をかけるのもひと苦労ですよね。
まずは、床にモノを直置きしないように気をつけ、通り道をしっかりと確保しましょう。
キッチンで使ったものをすぐにリビングに持っていけるよう、あるいはリビングで出たゴミをキッチンに運べるよう、一時置きのカゴやトレイなどを用意するのも、スムーズな動きを助けます。
モノの通り道をふさがないだけで、家事の効率はぐっと上がりますよ。
リビングや玄関で使えるワンアクション収納
ワンアクション収納とは、扉を開けたり、引き出しを引いたり、フタを取ったりする手間がなく、文字通り「一つの動作(アクション)」でモノを出し入れできる収納のことです。
忙しい毎日の中では、この「手間を減らす」工夫がとても役立ちます。なぜなら、動作が少ないほど、元に戻すハードルが下がり、片付けが続きやすくなるからです。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 玄関
鍵は、トレイに「置くだけ」。または壁のフックに「掛けるだけ」。
お子さんの帽子や上着も、手の届く高さのフックに「掛けるだけ」。 - リビング
テレビやエアコンのリモコンは、専用のスタンドやトレイに「立てるだけ」「置くだけ」。毎日届く郵便物やチラシは、確認するまで「一時的に入れるだけのボックス」を用意する。 - キッチン
よく使う調理器具(おたまやフライ返し)は、コンロ周りに「吊るすだけ」。
ラップやアルミホイルは、引き出しに立てて「取り出すだけ」。
特にお子さんや家族みんなが使う場所では、できるだけ簡単な収納方法を取り入れることが、散らかりにくさに直結します。
週末リセットで散かりを防ぐ
平日は忙しくて、なかなか隅々まで片付けが行き届かなくても仕方がありません。
そんな時は、週末に一度、家の中を「リセット(元の状態に戻す)」する日を決めておくのも一つの手です。
平日の間に少しずつ散らかってしまったモノたちを、定位置に戻してあげる時間です。
例えば、「土曜日の午前中の30分間」や「日曜日の夜、寝る前の1時間」など、ご家庭で時間を決めやすいタイミングで、家族みんなで取り組みます。
完璧を目指なくても大丈夫。
「リビングのテーブルの上だけは元に戻す」「玄関の靴を揃える」など、まずは一番目につく場所や、スッキリすると気持ちが良い場所から決めておくだけでも、週明けを清々しい気持ちでスタートできますよ。
このリセットの習慣が、大きな散らかりを防ぐ防波堤のような役割を果たしてくれます。
まとめ|家族のペースで続くシンプルライフへ
子どもがいてもスッキリとした暮らしを保つためには、たくさんの工夫や考え方があります。
でも、一番大切なのは、完璧を目指しすぎないことです。
日によって散らかったり、計画通りにいかなかったりすることもあります。
特にお子さんが小さい間は、思い通りにならないことのほうが多いかもしれません。
そんな日もあって当たり前です。
ご紹介したヒントの中で、ご自身の家庭に合いそうだな、と感じるものがあれば、まずは一つでも試してみてください。
試してみて合わなければ、別の方法を探してみれば良いのです。
ご家族みんなが笑顔で過ごせる、心地よいバランスを見つけながら、ご自身のペースで続くシンプルライフを、ゆっくりと育んでいきましょう。