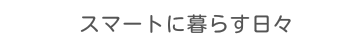毎日を過ごす中で、「もう少し時間があったらいいな」「なんだかいつも時間に追われている気がする」と感じることはありませんか。
やるべきことはたくさんあるのに、あっという間に一日が終わってしまうと、少し焦る気持ちになりますよね。
しかし、暮らしを大きく変えなくても、日常の中のちょっとした動作や手順を見直すだけで、驚くほど時間がスムーズに流れ始めることがあります。
それは、特別なことではなく、誰でもできる「小さな工夫」の積み重ねです。
この記事では、日々の生活の中で時間をつくりだし、心にゆとりをもたらすための「暮らしの整え方」や「考え方のヒント」を、いくつかの視点から丁寧にご紹介します。
大きな変化を目指すのではなく、ご自身のペースで試せそうなことから、気軽に取り入れてみてくださいね。
日常の段取りを整えて作業時間を短くする方法

日々の作業を始める前に、少しだけ段取りを整えておくことで、思った以上にスムーズに進むことがあります。
「段取り」とは、物事を行う順序や手順を前もって整えること。
このひと手間が、作業中の迷いや中断を減らし、結果として作業時間を短くすることにつながります。
ここでは、作業時間を短くするための段取りの整え方を見ていきましょう。
朝・夜のルーティンをシンプルに組み立てる
朝と夜の時間は、比較的、毎日決まって行うことが多いものです。
例えば、朝起きてから出かけるまで(洗顔、着替え、朝食など)、あるいは夜帰宅してから眠るまで(夕食、入浴、翌日の準備など)の行動です。
これらの決まった流れを「いつも行うこと」としてシンプルに決めておくと、次に何をしようかとその都度考える時間が減り、自然と体が動くようになります。
まずは、朝と夜に「必ず行うこと」を書き出してみることから始めてみましょう。
紙やノート、スマートフォンのメモ機能など、使いやすいもので構いません。
時系列に沿って、細かく書き出すことがポイントです。
次に、それをどの順番で行うと一番動きやすいか、流れを組み立ててみます。
例えば、「洗顔と歯磨きは洗面所でまとめて行う」「着替えのついでに翌日の服も出しておく」など、場所の移動が少なくなるように工夫したり、関連する作業をグループにしたりすると、効率的な流れが見つかりやすくなります。
大切なのは、完璧を目指しすぎないこと。あまりに細かく決めすぎると、それが負担になってしまうこともあります。
まずは「これだけは必ずこの順番で行う」という簡単な流れを決めておくだけでも、毎日のスタートや締めくくりが整いやすくなりますよ。
手を止めないための“流れ”のつくり方
一つの作業をしている最中に、別のことが気になって手を止めてしまうと、集中力が途切れてしまいがちです。
そして、再び元の作業に戻るまでに時間がかかってしまうことがあります。
そうならないためには、作業を一つの「流れ」として捉え、中断を減らす工夫をすることが大切です。
例えば、料理であれば、野菜を切る、調理する、お皿を準備する、といった一連の動作があります。
これらを始める前に、必要な道具(包丁、まな板、ボウルなど)や、使う予定の調味料を手の届く範囲にそろえておくと、作業の途中で何かを探すために手を止めることが少なくなります。
これは料理以外でも応用できます。
例えば、掃除機をかける前には、床に置いてあるものを片付け、必要なノズルを準備しておく。
デスクで作業を始める前には、必要な資料や筆記用具を手元にそろえておく。
このように、作業を中断しないための「小さな準備」が、一連の動作をスムーズな「流れ」にし、結果的に作業全体の時間を短縮する助けになります。
「作業を始める前に、最後まで終わらせるために必要なものを準備する」という意識を持つことが第一歩です。
迷いを減らす準備リストの活用
「あれは何が必要だったかな?」「手順はどうだっけ?」と考える時間は、意外と多くあるものです。
特に、普段あまりしないことや、準備するものが多いことについては、事前に「準備リスト」を作っておくと、当日の迷いを格段に減らすことができます。
例えば、週末にまとめて行う掃除の手順(場所ごとの掃除内容など)や、出かける前の持ち物、週に一度の買い出しリストなどです。
また、季節の変わり目に行う衣替えの手順や、たまにしか作らない料理のレシピなども、リスト化しておくと便利です。
リストにしておけば、それを見ながら一つひとつ確認するだけで良くなるため、頭の中で記憶をたどる時間が減り、忘れ物や手順の間違いも防ぎやすくなります。
リストは、一度作って終わりにするのではなく、使ってみて「この順番の方がやりやすい」「これも必要だった」と気づいたことがあれば、その都度更新していくと、さらに使いやすいリストになっていきます。
作ったリストは、ノートにまとめても良いですし、スマートフォンのアプリやクラウドサービスなどを活用して、いつでも見返せるようにしておくと便利ですね。
物の扱いを見直して時間ロスを減らす工夫

私たちは毎日、たくさんの物に触れて生活しています。
その物がどこにあるか分からなかったり、取り出しにくかったりすると、無意識のうちに時間をロスしていることがあります。
物の置き場所や管理の仕方を見直し、探し物にかかる時間を減らすことも、時間をつくるための大切な工夫です。
ここでは、物の扱いや整理に関する工夫をご紹介します。
よく使う物の置き場所を決めるポイント
「あれはどこに置いたかな?」と物を探す時間は、できるだけ減らしたいものですね。
そのためには、「よく使う物」の置き場所、つまり「定位置」をきちんと決めておくことが非常に効果的です。
置き場所を決めるポイントは、まず「使う場所の近くに置く」ことです。
例えば、玄関で使う鍵や印鑑は玄関に、リビングで使う爪切りやリモコンはリビングの決まった引き出しに、という具合です。
使う場所としまう場所が近いと、取り出すのも片付けるのも楽になります。
次に、「使用頻度」で置き場所を考えることも大切です。
毎日使うものは、一番取り出しやすい「一等地」(例えば、目線の高さや、かがまずに取れる場所)に置きます。
週に一度しか使わないものは、少し手間がかかる場所でも構いません。
また、「グルーピング(仲間分け)」も有効な方法です。
例えば、「コーヒーを淹れるための一式(豆、フィルター、ドリッパーなど)」「手紙を書くための一式(便箋、封筒、筆記用具など)」のように、一緒に行う作業で使うものをトレーや箱にまとめておくと、一度に準備が整います。
「しまいやすさ」も考慮しましょう。
フタを開けて、箱を出して、さらに中のケースを開けて…というように手順が多いと、戻すのが面倒になり、出しっぱなしの原因にもなりかねません。
よく使う物ほど、少ない動作(ワンアクション)で出し入れできるような収納方法を選ぶと、定位置管理が続けやすくなります。
作業がスムーズになる持ち物の整理法
外出先で必要な物がバッグの中で見つからず、焦ってしまったり、時間を取られてしまったりした経験はありませんか。
バッグの中身なども、作業をスムーズにするための大切な「場所」の一つです。
バッグの中を整理するには、小さなポーチやケースを活用して、種類ごとに分けておくと便利です。
例えば、「いつも持ち歩く衛生用品」「仕事で使う筆記具類」「充電器やイヤホンなどの電子機器類」など、目的別にまとめておきます。
こうすることで、バッグの中で物が迷子になるのを防ぎ、必要なものをすぐに見つけられるようになります。
ポーチを選ぶ際は、中身が外から見える透明なものやメッシュ素材のものを選ぶと、開けなくても中身が確認できるため、さらに探しやすくなります。
また、バッグを変える際も、ポーチごと移動させるだけなので、入れ忘れを防ぐことにもつながります。
バッグの中も、家の中と同じように「定位置」を決めることが大切です。
例えば、「お財布は内ポケットに」「鍵はキーホルダーにつけて指定の場所へ」と決めておくだけで、手探りでも必要なものを取り出せるようになります。
そして、一日の終わりにはバッグの中身を確認し、不要なレシートやゴミを取り出す習慣をつけると、いつも使いやすい状態を保てます。
後片付けを短時間で終わらせる小さな工夫
作業が終わった後の片付けは、できるだけ短時間で、気持ちよく終わらせたいものです。
後片付けが面倒に感じると、つい後回しにしてしまい、物が散らかった状態が続いてしまうこともあります。
後片付けを楽にするには、「使ったらすぐに戻す」という小さな習慣が何よりも役立ちます。
「すぐに戻す」を習慣化するためのコツは、前述の通り「戻しやすい場所」を定位置に設定することです。収納場所に余裕を持たせ、詰め込みすぎないようにすることも、戻しやすさにつながります。
また、汚れに関しては、「汚れが定着する前に対応する」ことが鉄則とされています。
例えば、コンロ周りに油が跳ねたら、温かいうちにさっと拭き取る。洗面台を使った後は、水滴をタオルで拭き取る。
このように、何かの「ついで」に小さな汚れを取り除いておくだけで、後でまとめて大掛かりな掃除をする手間が大きく変わってきます。
料理で使った調理器具も、すぐに洗えない場合は水につけておくだけで、汚れがこびりつくのを防ぎ、後で洗うのがずっと楽になります。
こうした「後を楽にする」ための小さな工夫の積み重ねが、日々の後片付けの時間を着実に短縮してくれます。
行動の順番と場所をそろえて毎日を進めやすくする

日々の暮らしの中での「動き方」にも、時間を生み出すヒントが隠されています。
家の中での移動経路、いわゆる「動線」を意識することで、無駄な動きを減らし、毎日をより進めやすくすることができます。
行動の順番と場所をそろえる、という考え方を見ていきましょう。
作業の“寄り道”をなくす動き方の工夫
家の中で行ったり来たりと、何度も同じ場所を通ったり、物を取りに戻ったりする「寄り道」のような動きは、知らず知らずのうちに時間を消費していることがあります。
このような「作業の寄り道」をなくすためには、自分の動き方を少し客観的に観察してみましょう。
例えば、朝の身支度なら、洗面所で顔を洗い、一度リビングに戻ってから、また洗面所の隣のクローゼットに着替えを取りに行く…といった動きをしていないでしょうか。
もしそうなら、洗面所で行うこと(歯磨き、洗顔など)と、クローゼット前で行うこと(着替え、持ち物準備など)を、それぞれまとめて行うように順番を工夫します。
あちこち移動する回数が減るだけで、一連の動作がとてもスムーズになります。
洗濯の際も、「洗濯機から洗濯物を取り出す→ベランダに干しに行く→乾いたものを取り込む→リビングでたたむ→各部屋のクローゼットにしまう」という流れを見直し、たたむ場所をクローゼットの近くにするなど、動線を短くする工夫が考えられます。
また、「ついでに運ぶ」習慣も有効です。
2階に上がる時には、2階に持っていくものを一緒に運ぶ。キッチンに行くときには、リビングにある使い終わったコップを持っていく。
こうした小さな意識づけが、無駄な往復を減らしてくれます。
家事や身支度をまとめて進めるための工夫
家事や身支度は、関連する作業を「まとめて」行うと効率的です。
あるいは、何かの「ついで」に別の作業を行う「ついで作業」を取り入れるのも良い方法です。
例えば、お風呂に入る前に、洗面所の鏡をさっと拭いたり、排水口のごみを取り除いたりする「ついで掃除」を習慣にします。
浴室から出る前に、壁や床にさっと水をかけておくだけでも、汚れの予防につながるとされています。
キッチンでお湯を沸かしている間や、電子レンジで加熱している間の「待ち時間」も活用できます。
その数分間で、次の日に使う野菜を少し切っておいたり、食器を数枚洗ったり、シンクを軽く磨いたりすることができます。
このように、何かを待っている時間や、一つの場所で行う作業に、別の小さな作業を組み合わせることで、別々に時間を取る必要がなくなります。
無理のない範囲で、「今、この場所で、他にできることはないか」と考えてみるのがコツです。
よく使う場所を使いやすく整える考え方
毎日何度も使う場所、例えばキッチン、洗面所、デスク周りなどは、特に使いやすく整えておくことが大切です。
場所が整っていると、そこで行う作業が自然とはかどり、作業に取りかかるまでの心理的なハードルも下がります。
例えば、キッチンの調理台は、できるだけ物を置かずに作業スペースを広く保つことが基本です。調味料や調理器具が出しっぱなしになっていると、まずそれを片付けるところから始めなくてはならず、手間がかかります。
よく使うものだけを厳選し、それ以外は収納場所にしまうようにします。
デスク周りも同様に、必要な文房具だけを厳選して取り出しやすい場所に置きます。
書類なども平積みにせず、立てて収納するなど、必要な情報がすぐに見つかる工夫をします。
洗面所であれば、毎日使う歯ブラシや化粧品などは、トレーにまとめるか、鏡の裏の収納など、すぐに手に取れる場所に置きます。
ストック品は別の場所に保管し、使う場所には必要最低限のものを置くようにすると、掃除もしやすくなります。
このように、作業する場所そのものを「いつでもすぐに使える状態」にしておくと、スムーズに動き出せるようになります。
まとめ
ここまで、日常の段取りや物の扱い、行動の順番など、時間をつくるためのさまざまな工夫を、具体的な方法や考え方と共にご紹介してきました。
どれも、日々の暮らしの中で意識を向けることで始められることばかりです。
最後に、これらの工夫を取り入れる上での大切な心構えをまとめます。
時間をつくる工夫は小さな調整から
「時間をつくる」と聞くと、何か大きな生活の変化や、特別な努力が必要だと感じてしまうかもしれません。
しかし、実際には、決してそんなことはありません。
大切なのは、日々の暮らしの中にある「ちょっとした不便」や「手間だと感じること」に気づき、それを少しだけ調整してみること。
物の置き場所を10cm変える、作業の順番を入れ替えてみる。
それだけの「小さな調整」が、思いがけず作業をスムーズにしてくれることがあります。
一つの作業が5分早くなるだけでも、一日にいくつかの作業が積み重ねれば、それは大きなゆとりにつながります。
まずは、完璧を目指せずに、一つでも「これなら試せそう」と思える小さな調整から始めてみませんか。
続けやすい形で見直すことがポイント
取り入れた工夫が、もし「自分には合わないな」「かえって手間が増えた気がする」と感じたら、無理に続ける必要はありません。
人によって、やりやすい方法や心地よいと感じるペースは異なります。また、暮らし方や家族の状況、体調などは変化していくものです。
以前は合っていた方法が、今も最適とは限りません。
大切なのは、その時々の自分にとって「続けやすい形」であること。
時々立ち止まって、今のやり方を見直してみる。
季節の変わり目や、生活のリズムが変わった時などが、見直しの良いタイミングかもしれません。
そうして自身に合った方法を柔軟に見つけていくことが、心地よい暮らしと時間のゆとりを育んでいくことにつながっていくはずです。